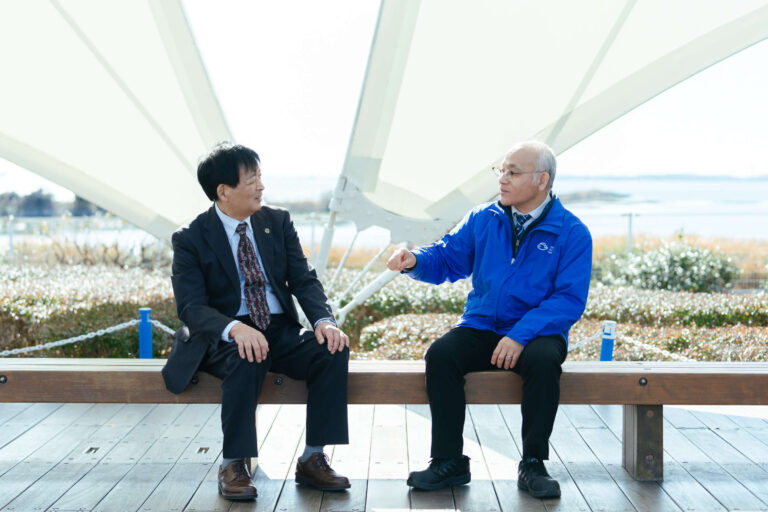TALK
水族館に求められる教育の役割と、葛西臨海水族園が大切にしていること(前編)
2025.03.31
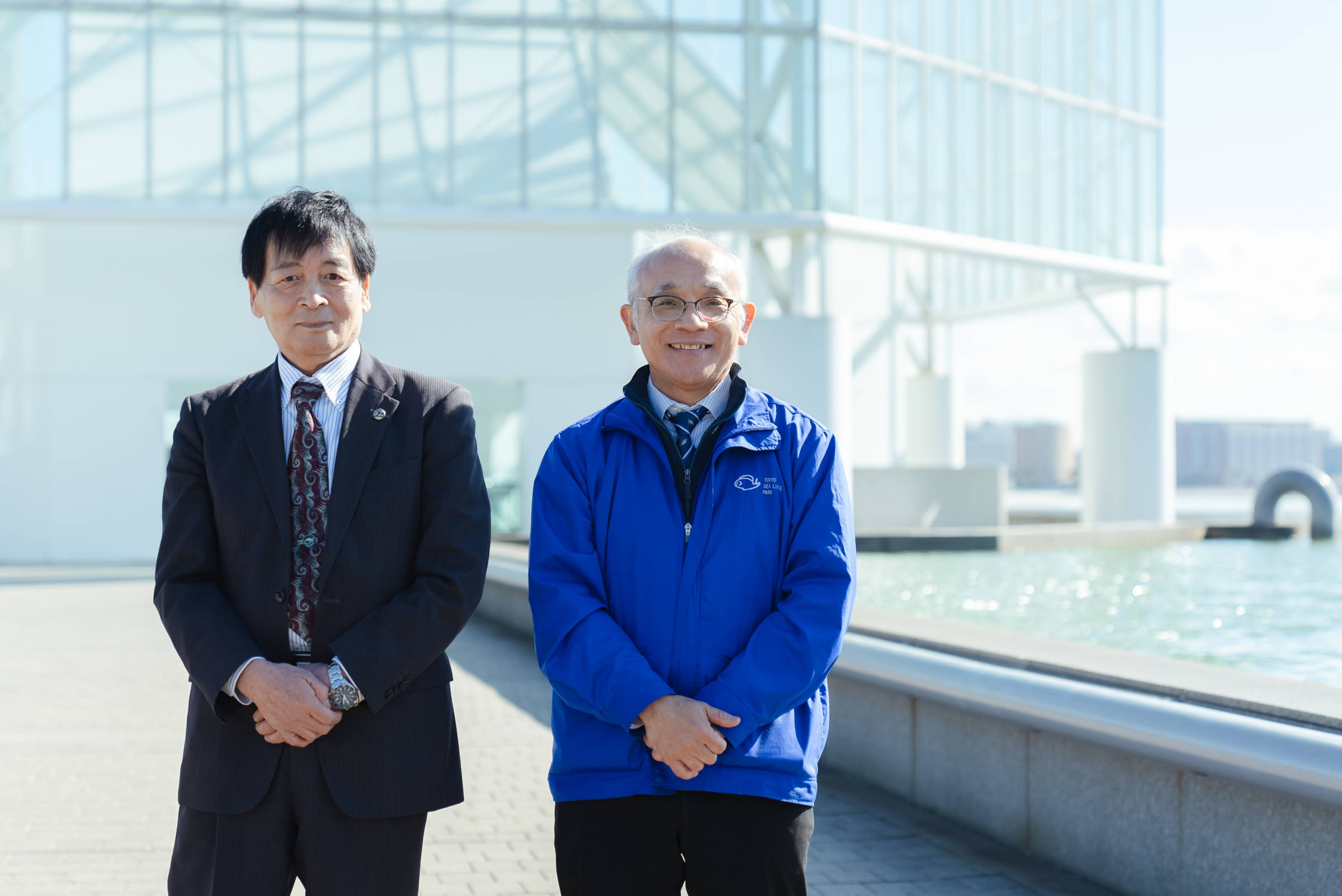
大分マリーンパレス水族館うみたまご、マリンワールド海の中道館長を経て、日本初の「水族館における海洋教育に関する研究」で博士号を取得された高田さん。
小笠原水産センター、恩賜上野動物園、多摩動物公園などを経て葛西臨海水族園の園長を務める錦織さん。
水族館に長年携わられたお二人に、2024年に35周年を迎えた葛西臨海水族園が大切にしてきたことについて語っていただきました。
葛西臨海水族園。誕生からリニューアルへ
-
錦織:
葛西臨海水族園は1989年にこの地(東京都江戸川区)でオープンしました。もともとは上野動物園の中につくられた日本初の水族館施設でしたが、上野動物園開園100周年記念事業として場所を移して独立させようと、葛西に設置されたことがはじまりです。
振り返ると、開園前のこの場所は荒野が広がっている埋め立て地でした。そこに都民の憩いの場となる水族園や公園施設、海辺には人工の渚を造成していき、そこに生き物が帰ってくることを願う、そういう場所として誕生しました。

-
高田:
じつは葛西臨海水族園と、私が最も長く勤めていた福岡の水族館「マリンワールド海の中道」は同級生で、同じ1989年にオープンしています。海の中道が3月で、葛西臨海水族園が10月なので、「マリンワールド海の中道」が半年だけ先輩ということになります。
ただ、海の中道はオープンしたときには建物の半分が未完成だったこともあり、葛西臨海水族園を“脅威”に感じていました。水族館はどういう生物を集めているか、どんな大きさの水槽を持っているか、どのくらいの広さがあるかということが評価の指標になり、そこがとても充実していたからです。

-
錦織:
当時、葛西臨海水族園が掲げたコンセプトは「海と人間の交流の場」でした。
都市である東京は自然環境を犠牲にしてきた面があると思います。そこから「葛西では何かできることはないか」と考えて「再生」に取り組んできた背景があります。何かを「守っていこう」というよりも、「新たに自然環境をつくって戻していこう」という考え方であり、そのひとつの象徴がこの葛西臨海水族園なのです。

-
錦織:
水族園は東京の臨海部にあり、海と人をどうつないでいくのか。その交流の場という考え方は今日まで続いており、その志は今勤めている私たちスタッフも大切にしているものです。これまでの環境や時代の変化に合わせて少しずつ姿を変えてきているところがありながらも、コンセプトは維持してきました。
高田:私は当時、「マリンワールド海の中道」の残り半分がオープンする1995年に向けて、葛西臨海水族園にないものを特色として何かつくれないかという思いで、何度も足を運んで勉強させていただいていました。
葛西臨海水族園は当時のテーマが「7つの海」でしたよね。北極なども含めた世界中の海をテーマにしていて、館内を巡ると図鑑でも見たことのない生物がいました。生物収集にかける情熱とか能力に驚き、すごいコレクションだなと思ったことが正直な感想でしたね。
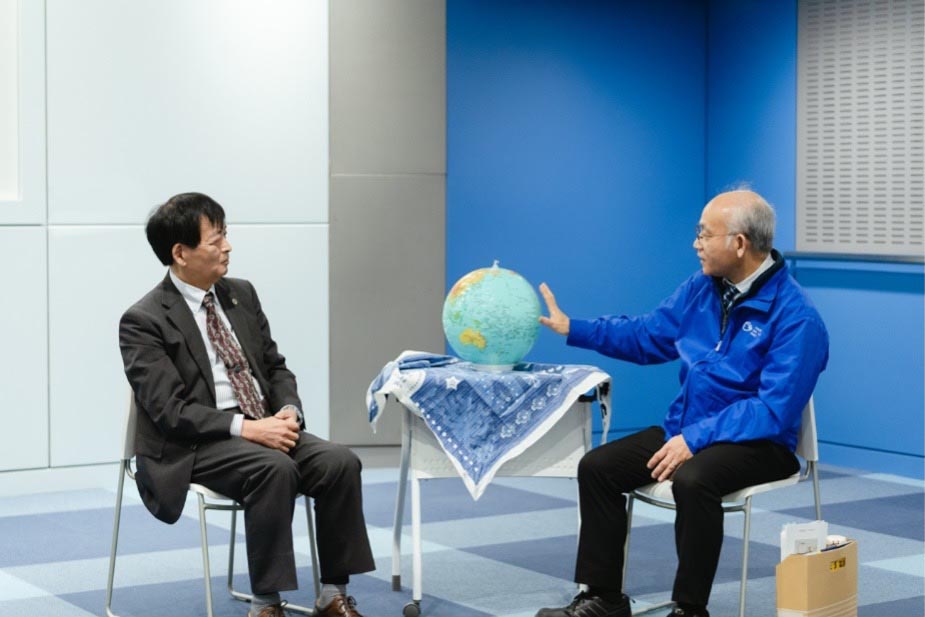
-
錦織:
ありがとうございます。7つの海の展示は、35年経った今でも変わらず大切に守ってきた展示のひとつです。
一方で、様々な方に来園いただくためには、時代に合わせて変えていくべきこともありますが、それが十分にできていないこともあります。
具体的に言えば、館内は十分なユニバーサルデザインになっていないかもしれません。つまり、現在のこの施設でできることの限界を感じているのです。
そこで、葛西臨海水族園は2028年に向けてリニューアルを進めています。私たちが感じてきた課題をひとつずつクリアしていき、より多くの方、今まで来ることができなかった方にもご利用いただける水族園になるよう願っています。
水族館は「社会教育施設」
-
錦織:
高田先生は水族館における活動に限らず、様々なところでその情報や魅力を伝える活動、また教育の面から水族館をさらに発展させていこうという活動に取り組まれていて素晴らしいと思います。
本日は情報発信や教育についてのお話をお聞きし、勉強させていただきながら、良いところはどんどん取り入れさせていただきたいと考えております。


-
高田:
教育の面では「博物館法」という法律があり、水族館は広い意味で博物館の一種であると定められています。つまり、博物館と同様に社会教育施設という位置付けですね。
私が「マリンワールド海の中道」の前に勤めていた「大分マリーンパレス水族館うみたまご」では、大分の水族館で初の学芸員採用となり、水族館から「教育に取り組んでほしい」と言われたことをはじまりに、現在に至るまで教育部門に取り組んできた背景があります。
当時、博物館について調べていくと、「博学連携」や「学社融合」という言葉が出てきて、学校教育と博物館を融合・連携して授業を行うという流れがありました。そのときに私は「教育は義務教育で終わりではなく、死ぬまで学びは続く。教育のマーケットは無限にある」と思いました。
水族館にレクリエーションやレジャーで訪れるお客様だけでなく、教育目的で来られる方にも我々はきちんと対応して、提供できるものを持っておきたいという思いで教育にかなり力を入れてきました。錦織:教育に関しては、葛西臨海水族園では、「野生生物保全」「環境」「調査研究」の3点について、いろいろな取組を行っています。
特に野生生物保全は、待ったなしの目の前の大きい課題と捉えており、それを広めるためには、環境など様々なものを合わせて伝えていく必要があります。
今までは希少な野生動物の保全を重視していましたが、それだけでは不十分と考えるようになりました。いわゆる普通の生き物がくらせる環境を保つこと、生物多様性の保全に大きくシフトしてきている現状があります。
希少種を守ろうということは伝えつつも、身近にある自然を見る・守る視点こそが大切だと伝えています。
何かひとつでも持ち帰ってもらうものがあればいい

-
高田:
情報発信はとても重要ですよね。「マリンワールド海の中道」の立ち上げ時に残り半分の水族館をどうつくろうと考えていて、葛西臨海水族園と友好提携を結んでいるアメリカのモントレーベイ水族館の視察に行ったことがあります。
展示のデザインやフレンドリーな案内、ボランティアさんの献身的な説明を受け、それがとても楽しくて、「楽しく学ぶことが大切だな」と思いました。学びは難しい、勉強と言われると距離が生まれてしまいます。
そこで海の中道では、お客様との交流や情報発信の中で楽しい学びが起こるように意識して取り組んでいました。錦織:水族館に足を運ぶ人の多くは「教育を受けたい」と思ってくることは少なくて、楽しそうだから行ってみよう、または暇つぶしで来る人もたくさんいると思います。
むしろ私はそういった「関心がないけれども来ちゃった」という方に、何かちょっとでも持って帰ってもらうものがあれば良いと思っているんです。何かひとつで良いんですよ。
先ほど高田先生から博物館の話がありましたが、自然史博物館などとの大きな違いは、水族館には生きた生き物がいることです。
運営側の私たちは「こういうことを伝えよう」と思うのですが、そのとおりに伝わらないんですよね、生き物だから。想定していないことや偶然が常に起きていて、それこそが生き物がそこにいることのひとつの価値かもしれないと思っています。高田:確かにそのとおりですね。
錦織:私はそれを大切にしたいと思っています。私たちが発見していないことを、来てくださったお客様が発見する、あるいは私たちが伝えようと思っていることとは違うものを見ていただけるかもしれない。それで私は良いと考えています。
水族館の中で私は生き物に関する疑問を全て解決しなくても良いと思っているんですよ。「関心がなかったけれど水族館に行ったら楽しかったね、そういえばあれってなんだったんだろう」、そう思ってもらえたら次につながる可能性があるし、うちの近くの水辺にも何か魚がいるかなと興味を持ってもらえたら、それだけでうれしいですね。
【プロフィール】

高田 浩二(たかだ こうじ)
1953年生まれ。海と博物館研究所所長。
大分生態水族館(現マリーンパレス)入社。
その後、マリンワールド海の中道に転職し、同館の設立に携わる。
2004年から 2015年まで同館の館長を務める。
2005年に日本初の「水族館における海洋教育に関する研究」で博士号を取得。
元福山大学生命工学部教授。
好きな水族:カメ。カメグッズのコレクターで、オフィスはカメグッズであふれています!
水族館に行くとここを見てしまう:展示ごとに何を伝えたいかを探しています。その水族館のメッセージを受け取りたい!

錦織 一臣(にしきおり かずおみ)
1968年生まれ。葛西臨海水族園園長。
東京水産大学(現東京海洋大学)水産学部卒。
福島大学大学院地域政策科学研究科修了。
東京都職員として、伊豆大島や小笠原諸島の父島などの各地で勤務。
その後、恩賜上野動物園、多摩動物公園などの勤務を経て現在に至る。
好きな水族:イセエビ。1年近くの長い浮遊幼生期をへて稚エビになる生態が興味深い。
水族館に行くとここを見てしまう:その時の気持ちの赴くままに…そして気になった水槽は時間をとってじっくり観察します!