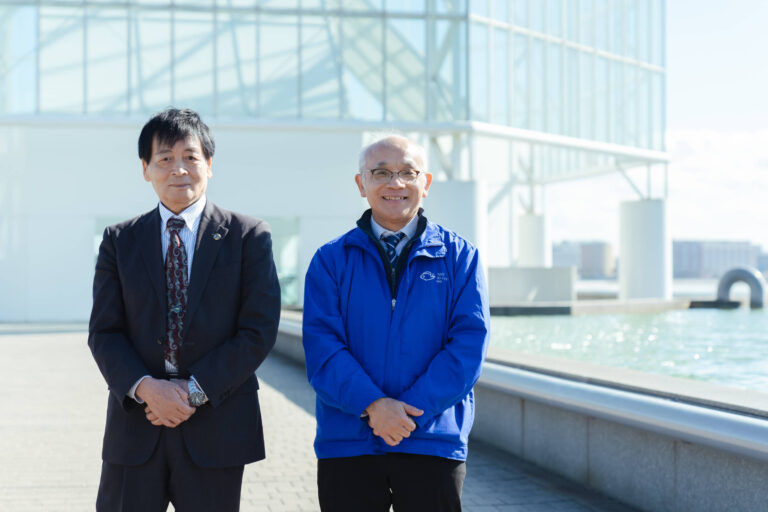TALK
水族館に求められる教育の役割と、葛西臨海水族園が大切にしていること(後編)
2025.04.27

水族館は教育機関であり、「地域連携共育」の重要性を説く高田さんと、水族館はなくてはならない存在、あると世の中や地球が少し良くなる存在でありたいと願う錦織さんに、「海」と「人」の共生を体現する水族館の在り方や「新たな水族園が描く未来」について語り合っていただきました。
水族館の存在価値を高める「アクアポジティブ」の考え方
-
高田:
錦織園長は「アクアポジティブ」の考え方を掲げて、葛西臨海水族園の運営に取り組まれていますね。簡単にその内容を教えていただけますか。
錦織:現在は生物多様性保全の話の中で「ネイチャーポジティブ」という言葉が使われています。何か希少な生き物を守ろうという取組よりも、むしろ身近にある自然を増やそう、豊かにしていこうというところから出てきた言葉だと私は理解しています。
それを水族館に置き換えて考えたときにも、この考え方を発展させる可能性があると思いました。
例えば、来園者にご覧いただいている水槽は、その後ろに巨大な設備があり、マグロの水槽1個の後ろでは365日24時間、ろ過循環システムが動いて温度調整を行い、多くのエネルギーを使っています。ほかにも、設備メンテナンスを含め、たくさんの資源を使って水族園が成り立っているという現実があります。
アクアポジティブの考え方は、ここにアプローチしたいと思っています。高田:なるほど。それはどのようにですか?
錦織:葛西臨海水族園で使用する電気エネルギーは自分のところでつくっているわけではありませんが自然再生エネルギーです。プラスチックなどの資源は使い捨てにならないように、そこも極限まで取り組んでいます。

水族館はこれまで「誰のものではなかったのか?」
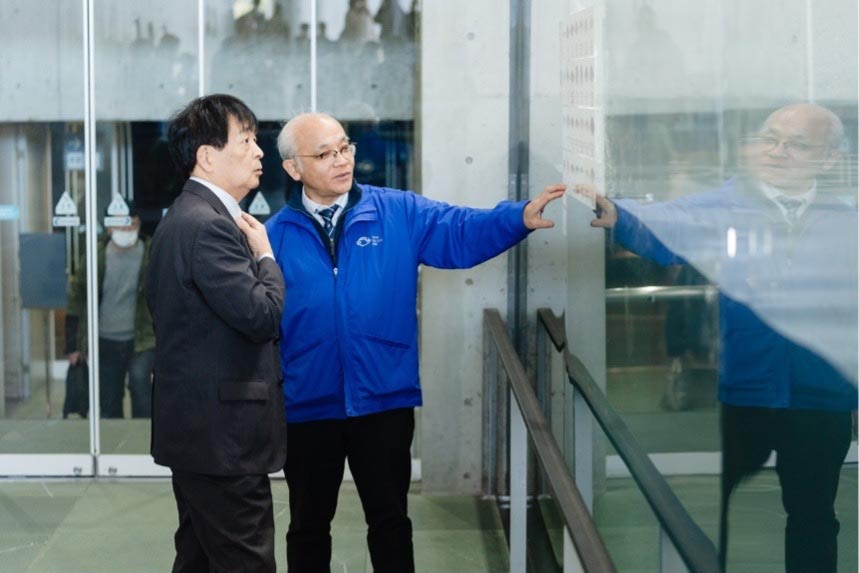
-
錦織:
リニューアルを進めている新しい葛西臨海水族園では、新たな理念「海と接する機会を創出し、海と人とのつながりを通して海への理解を深める水族園」に基づいて、「生命(いのち)と幸せを紡ぎ続ける水族園」というコンセプトが事業者から提案されています。
私なりにこれを解釈するとウェルビーイング(持続的で良好な状態)の概念とつながります。単純なハッピーというよりも、その人、その場所、地球、生き物、様々なところがより良くなるというイメージですね。
葛西臨海水族園が普段取り組んでいることがそういったところに結びついていけると考えると、非常にワクワクしますし、面白そうだと感じています。もしかすると、これから先の動物園、水族館が目指す指標のひとつになるようにも感じています。高田:すてきなコンセプトですね。葛西臨海水族園はたくさんの人に利用される水族館なので、人が集まってきたときには人同士の交流、つまりコミュニティが生まれますよね。
水族館に行くのは生物を見たいという目的が前提としてあるものですが、水族館に行っていろいろな人と交流できるコミュニティに参加したい、人の輪の中に加わりたいという思いは多くの方がもつものです。
「生物を見に行く水族館」から「コミュニティとしての水族館」へ。リニューアル後の葛西臨海水族園はそういう水族館であってほしいと思っています。
また、リニューアルに向けては今まさに整備が始まり、建物や水槽のデザインだけでなく、空間、学び、さらに時間軸など、いろいろなものをセットにしてデザインされた水族園であってほしいという希望があります。これからの水族館はそういったものが求められていくと思います。錦織:私も来園者に対話と様々な体験をしてもらいたいという思いがあります。それを考えたときに現在は「体験の格差」がかなりあると感じますね。
ひとつの問いとして「公営の水族館は誰のものか」を掲げて話をすると、「みんなのもの」という答えが返ってきます。では「みんな」とは誰を指すのか?
同時に「これまで水族館は誰のものではなかったのか」という問いを立てることもできます。「みんな」に入っていなかった人を考えて、そこにアプローチしていくことが重要です。
今回の対談の冒頭の方で「多くの人に来てもらいたい」と話しました。今は館内のデザインを事業者の方々が一生懸命取り組んでくれています。常に「誰のものではなかったのか」という視点を頭に入れながら、多くの人を包摂できる場所になればと思っています。
東京にある水族館だからこそ、伝えられること

-
高田:
私は2025年1月下旬に台湾の国立博物館のツアーに行ってきて、自然史、科学、海洋などと領域がじつに幅広く、とても充実していることに驚いて帰ってきました。
日本、そして東京を代表する存在である葛西臨海水族園には、自然史と海が合体したような、これまでに見たことがない視点の発見があり、会話が弾むような水族館になってほしいと思っています。錦織:東京という視点で考えると、東京は日本の経済の中心地である大都市であり、最も人口が多い場所です。
そして、東京都にある葛西臨海水族園にとってもうひとつ大切な視点は、東京都は小笠原諸島など多くの島があり、47都道府県で最も広い海を有しているということです。じつは東京の大部分が海なんですが、そのことはあまり知られていないため、東京の海の魅力を伝え続けていく必要があると思っています。高田:そうですよね。日本は領海を含めた「排他的経済水域EEZ」の面積では世界で6位です。小さな島なのにこれだけ上位に入っているのは東京都の存在がとても大きい。これからの時代こそ、海、生物、地球、全てがより良くなるためにも、日本一海を有する東京都の水族館として葛西臨海水族園が果たす役割は大きいかもしれません。
錦織:リニューアル後は、生き物に限らず、人と海との関係や海そのものについても伝えていく取組を充実させていってほしいと考えています。本日はありがとうございました。
【プロフィール】

高田 浩二(たかだ こうじ)
1953年生まれ。海と博物館研究所所長。
大分生態水族館(現マリーンパレス)入社。
その後、マリンワールド海の中道に転職し、同館の設立に携わる。
2004年から2015年まで同館の館長を務める。
2005年に日本初の「水族館における海洋教育に関する研究」で博士号を取得。
元福山大学生命工学部教授。
好きな水族:カメ。カメグッズのコレクターで、オフィスはカメグッズであふれています!
水族館に行くとここを見てしまう:展示ごとに何を伝えたいかを探しています。その水族館のメッセージを受け取りたい!

錦織 一臣(にしきおり かずおみ)
1968年生まれ。葛西臨海水族園園長。
東京水産大学(現東京海洋大学)水産学部卒。
福島大学大学院地域政策科学研究科修了。
東京都職員として、伊豆大島や小笠原諸島の父島などの各地で勤務。
その後、恩賜上野動物園、多摩動物公園などの勤務を経て現在に至る。
好きな水族:イセエビ。1年近くの長い浮遊幼生期をへて稚エビになる生態が興味深い。
水族館に行くとここを見てしまう:その時の気持ちの赴くままに…そして気になった水槽は時間をとってじっくり観察します!